「社内情報共有に適したおすすめのツールを知りたい」という人もいるかと思います。操作が簡単なこと・メンバー間で共有しやすいこと・同時に編集できることが、使いやすいツールの特徴として挙げられます。選定するときはそれらの機能が搭載されているかはもちろん、自社の用途や目的に沿って選ぶことが大切です。
本記事では、おすすめの社内情報共有ツールとして下記15個を紹介すると共に、社内情報共有ツールの概要・主な種類・メリット・選定ポイントについて詳しく解説します。
| 名前 | 特徴 |
|---|---|
| NotePM | ・マニュアル作成・ナレッジ共有も簡単 ・全国で7,000社以上が登録済 ・30日間すべての機能を無料お試し可能 |
| esa | ・全員で情報を育てる、同時編集エディタも搭載 ・バージョン管理・ロールバックも容易 ・60日間無料お試し可能 |
| Qiita:TEAM | ・こまめな情報共有で生産性を高められる ・Markdown記法に対応したプレーンテキストで記載 ・7日間の無料トライアル可能 |
| ナレカン | ・テキストベースのナレッジを気軽に保存可能 ・検索スピード平均0.2秒のキーワード検索を利用できる ・AIのチャット機能を用いた検索も可能 |
| Slack | ・ビジネス用のメッセージアプリケーション ・チャンネルというスペースでメンバーとやり取り可能 ・無料で利用可能(一部機能制限有) |
| Chatwork | ・誰でも簡単に使えるシンプルな機能を搭載 ・国内利用者数No.1(2024年4月時点)のビジネスチャットツール ・無料で利用可能 |
| LINE WORKS | ・有料ビジネスチャットとして2023年度シェアNo1を達成 ・業務効率化に必要な機能をアプリに集結 ・30ユーザーまで無料で利用可能 |
| Microsoft 365 | ・選択プランで利用可能なアプリケーションが異なる ・ソフトウェアはすべて自動更新対象 ・1ヶ月間の無料トライアル期間有 |
| Google Workspace | ・機能間のシームレスな連携も可能 ・安全な最新鋭のセキュリティ環境で利用可能 ・14日間の無料トライアル可能 |
| サイボウズ Office | ・累計導入社数70,000社を突破 ・20年以上ユーザーのニーズに合わせて進化 ・30日間すべての機能を無料お試し可能 |
| desknet’s NEO | ・どのような組織にもフィットするグループウェア ・業務アプリ作成など拡張機能を用意 ・30日間の無料トライアル可能 |
| Dropbox Business | ・7億人以上のユーザーから信頼されているサービス ・ファイルの安全な保護と業界をリードする使いやすさを実現 ・30日間の無料お試しが可能 |
| セキュアSAMBA | ・8,000社以上が導入しており、継続率98%を達成 ・デスクトップアプリの利用で、ファイルの直接編集や保存も簡単 ・無料で利用可能なフリープラン有(容量1GB 2名まで) |
| Fleekdrive | ・URLを共有することでファイルを共有できるオンラインストレージ ・社外の人とも安全にファイルを共有できる ・ルーティン業務を自動化できる |
| Stock | ・画像付きの情報を管理できる ・オフライン環境でも一部の機能を利用可能 ・タスク管理の機能も搭載 |
>関連記事:情報共有ツールおすすめ 33選(無料あり)と会社にもたらすメリット
社内のストック情報をすぐに見つけられる管理ツール「NotePM」
目次
社内情報共有ツールとは
社内情報共有ツールとは、組織内のメンバーが業務を進めていく上で、必要な情報を効率的に共有し、コミュニケーションを活性化するためのツールです。ツールを導入する主な目的として、蓄積された情報を共有しやすくすることや、仕事の効率アップが挙げられます。
情報共有ツールには、リアルタイムのコミュニケーションを可能にするチャット形式や、蓄積されたファイルのアクセス設定・編集・共有を容易にするストレージ型があります。また、重要な情報やノウハウをツールで管理し、チームメンバーが必要な情報を容易に見つけられる、ナレッジ共有型のツールも活用しやすいです。
社内情報共有ツールは、情報を迅速かつ効率的に共有でき、組織の生産性と協力を促進することで、よりスムーズな業務遂行を実現します。
>関連記事:社内wikiツールおすすめ15選【2025年最新】有料・無料プランを詳しく紹介
社内のストック情報をすぐに見つけられる管理ツール「NotePM」
社内情報共有ツールの主な種類
社内情報共有ツールは、搭載されている機能によって、下記の4つのタイプにわかれます。ここからは、それぞれのタイプの詳細を解説します。
- 社内Wiki
- ビジネスチャット・SNS
- グループウェア
- オンラインストレージ
社内情報共有ツールの導入を考えている人は、各種類の特徴を把握し、どれが自社に合っているか考えてみましょう。
社内Wiki
社内Wikiは、Webページに社内の知識や情報などを共有して、多くのユーザーによる編集・更新を可能とするツールです。社内情報共有ツールとしての社内Wikiは、組織内のナレッジを共有・管理・検索することに活用できます。誰でも編集や追加を行うことが可能なため、すべてのメンバーが知識や情報を共有し、社内の知識を一元化できるというメリットがあります。
社内Wikiには、過去の編集履歴を保存しているため、必要に応じて以前のバージョンの復元も可能です。また、強力な検索機能もあり、従業員は必要な情報を素早く見つけ出せます。社内Wikiはナレッジベースを作成し、社内にちらばる情報を管理するのに適したツールです。
ビジネスチャット・SNS
ビジネスチャット・SNSは、文字と画像メッセージを配信し、リアルタイムにメンバーとのコミュニケーションを可能とするツールです。チームメンバー間でのコミュニケーションを迅速にするだけでなく、知識共有・プロジェクト管理・ファイル共有など、多くの機能を備えています。多くのビジネスチャット・SNSでは、チャンネルやスレッドを作成することで、特定のトピックやプロジェクトに関連する会話が可能です。
ビジネスチャット・SNSだけでなくツールを導入すると、組織内でのリアルタイムな情報共有に大いに役立ちます。
グループウェア
グループウェアとは、組織内の情報共有・コミュニケーションをはじめ、幅広い業務を効率化するためのサービスです。グループウェアには従業員間でのメール送受信・予定表管理・会議スケジューリング・タスク管理など豊富な機能があります。中には業務プロセスを自動化し、承認フローなどの手続きを効率化するワークフロー機能も備わっています。
社内の重要な情報の共有や、蓄積された文書・ファイルの検索・参照も可能です。グループウェアは組織内での情報共有に役立ち、生産性の向上・業務の効率化を実現できます。
オンラインストレージ
オンラインストレージは、インターネットを通じてデータを保存・共有・管理できるサービスです。データをクラウドに保存するため、どこからでもアクセスできます。リモートワークなど、多様な働き方が浸透している近年において重要といえるでしょう。
インターネット接続さえあれば、どのような端末からでも格納されたファイルにアクセスできます。ファイルを他の従業員と共有しながら、リアルタイムでの共同作業も可能です。ファイルの変更履歴も保存されるため、編集・更新など作業の進捗も確認しやすくなります。
オンラインストレージは、働く場所に捉われずに業務遂行が可能なため、多くの企業が活用しています。
社内情報共有ツールを利用するメリット
ここからは、社内情報共有ツールを利用するメリットとして、下記の4点を紹介します。
- 社内状況の可視化
- 情報共有のスピード向上
- コミュニケーション活性化
- 属人化防止
利用するメリットを把握することで、社内情報共有ツールを導入するかどうかの判断材料にできます。社内情報共有ツールの導入を迷っている人は、ぜひ確認しておきましょう。
社内状況の可視化
社内情報共有ツールの使用により、社内の状況が可視化され、組織全体での業務効率が向上します。たとえば、「各従業員が何に取り組んでいるのか」「どのような問題に直面しているのか」「どのプロジェクトが進行中でどの程度進捗しているのか」などをリアルタイムに可視化できます。他にも、各プロジェクトのタスクの担当者・期限・優先順位も確認可能です。
社内状況の可視化により作業の重複を避け、リソースを有効に配分できるため、業務の効率化と生産性の向上につなげられます。
情報共有のスピード向上
社内情報共有ツールはリアルタイムで情報を送受信できるため、場所や時間に制限されない情報共有が可能です。そのため、情報共有のスピードが向上し、従業員間のコミュニケーションを迅速かつ効率的に行えます。
たとえば、プロジェクトに関する重要な連絡事項があった場合、従来は会議のスケジューリングを行って全員がそろってから周知する必要がありました。しかし、社内情報共有ツールを使用すると、重要な情報をすぐ全員に共有してフィードバックを受け取れます。これにより、意思決定のスピードの大幅に向上が可能です。
コミュニケーション活性化
社内情報共有ツールは、すべての従業員が意見やアイデアを自由に共有できるプラットフォームです。
たとえば、社内のチャットツールやフォーラムを通じて、従業員はプロジェクトのアイデアの即時的な共有や問題解決策の提示ができます。また、社内ツールにはリアクションやコメントの機能があるため、メールなどに比べて会話が活発化しやすいです。
すべての従業員が自由に意見できるため、社内情報共有ツールの利用はコミュニケーションの活性化を実現します。
属人化防止
社内情報共有ツールを導入すれば、すべての従業員が同じ情報へアクセス可能です。情報が一元管理されているため、全員が同じツールを経由して、業務対応に関する情報を調べられます。
たとえば、重要な技術情報を特定の個人のみで抱えていると、そのメンバーが異動・退職した場合にほかのメンバーに負担がかかります。社内情報共有ツールを導入することで、重要な技術情報が全員がアクセスできる場所に蓄積されるため、特定の個人がいなくても業務の進行が可能です。社内情報共有ツールがあれば、特定の個人・グループの業務の属人化を防げます。
>関連記事:ナレッジ共有ツールおすすめ16選を比較(無料あり)|導入メリットや評判、導入事例も紹介
社内のストック情報をすぐに見つけられる管理ツール「NotePM」
社内情報共有ツールを使用する際の注意点
社内情報共有ツールを使用する際は、導入や運用において、いくつか注意点があります。具体的には下記の通りです。
- 導入作業を計画的に行う
- 運用ルールを整える
- 情報漏洩のリスクを理解する
- 情報共有する際の誤操作に注意する
ここからは、それぞれの注意点の詳細を解説します。情報共有ツールの導入を検討している人は、各注意点を頭に入れたうえで運用しましょう。
導入作業を計画的に行う
社内情報共有ツールを利用するにあたって、社内への導入作業を行う必要があります。導入作業においては、ツールの設定や操作方法の説明などの作業が必要です。
とくに操作方法の説明は、社内情報共有ツールの仕様によっては時間がかかりやすいポイントです。導入の際に社内情報共有ツールの仕様をよく把握し「操作が複雑であるかどうか」「どういった形で説明するのが良いか」などを考えましょう。導入作業の進め方を考えておくと、社内情報共有ツールをスムーズに浸透させやすいです。
運用ルールを整える
社内情報共有ツールの運用ルールとして、共有する情報の内容や、共有の仕方などを定める必要があります。運用ルールが明確になっていないと、ツール内に不要な情報があふれたり、ドキュメントの命名規則が人によって異なったりする事態が発生しやすいです。その結果、欲しい情報が探しにくくなります。
運用ルールを定めることで、情報をわかりやすく整理でき、社内情報共有ツールがより使いやすくなります。運用ルールは定期的に見直し、適宜改善することも忘れないようにしましょう。
情報漏洩のリスクを理解する
社内情報共有ツールはセキュリティ対策を施しているものも多いですが、人間が扱う以上、情報漏洩に注意が必要です。ID・パスワードの管理が甘かったり、アクセス権限を不必要に多くの人に与えたりすることで、機密情報が流出する可能性が高まります。
社内情報共有ツールの導入前に、運用ルールとともにセキュリティ意識を高める使用方法も策定しておきましょう。また、万が一情報漏洩が発生した場合、どういった対応策を取るのかを考えることも重要です。
情報共有する際の誤操作に注意する
情報共有の際の誤操作により、意図しない相手への情報共有や誤った情報の共有を行ってしまうと、共有内容を修正する手間が発生します。情報共有を行う際は、情報の共有先や共有する内容を一度見直し、間違いがないことを確認したうえで共有しましょう。
場合によっては、ツールを使って社外の人に情報を共有するケースもあります。誤操作により社外の人と機密情報を共有してしまうと、大きな問題になりかねません。社外の人と情報共有ツールを使用する際は、とくに注意して操作しましょう。
社内情報共有ツールの選定ポイント
社内情報共有ツールはさまざまな種類が存在するため、どれを導入するか迷いやすいです。選定ポイントを押さえておくと、導入する情報共有ツールをスムーズに決められます。ここからは、社内情報共有ツールの選定ポイントとして、下記の5点を紹介します。
- 操作性
- 機能
- コスト
- 多言語対応の有無
- 安全性
社内情報共有ツールを導入する予定の人は、選定ポイントをあらかじめ把握しておきましょう。
操作性
社内情報共有ツールは、直感的に操作でき、すべての従業員が簡単に理解し操作できる必要があります。複雑で難解なツールは使用率を下げ、情報共有の効率を損なう可能性があるからです。
たとえば、チャット機能・ファイル共有・ビデオ会議など各機能へのアクセスが簡単なツールは、多くの従業員が利用しやすいでしょう。社内情報共有ツールを選定する際には、操作性に優れて使いやすく、情報の共有を容易にできることが重要です。
機能
社内情報共有ツールには、Wiki・ビジネスチャット・オンラインストレージ・ファイル共有・ビデオ会議・タスク管理など、さまざまな種類があります。自社のニーズに合った機能が搭載されたツールを選択することで、情報共有を簡単に実現するとともに、組織の効率的なコミュニケーションが可能です。
たとえば、プロジェクト管理機能を持つツールは、チーム全員がタスクを追跡してデッドラインを管理することに役立ちます。一方、ビデオ会議機能を持つツールは、リモートワークをしている従業員とのコミュニケーションやコラボレーションを促進する特徴があります。
社内情報共有ツールを選ぶときは、ツールが自社のニーズに対応できるかどうかを判断するために、機能をしっかりと確認することが重要です。
コスト
社内情報共有ツールを選択するときは、予算内に収まるかを確認しましょう。初期導入費用はもちろん、運用・メンテナンス・アップグレードなど、長期的な視点で見て判断することが必要です。
豊富で魅力的な機能が搭載されていても、料金が組織の予算を超えているなら適切なツールではありません。また、初期費用が低いツールであっても運用やメンテナンス費用が高い場合、長期的に見てコストがかかる可能性があります。
導入時に想定される効果に対して、コストが適切かを確認しましょう。
多言語対応の有無
グローバルに事業を展開している企業や、外国籍の従業員が多い企業においては、多言語対応の有無は重要です。ツールが多言語に対応していれば、外国の人とスムーズに情報共有できます。翻訳機能や、多言語でのインターフェース表示などがあるかを確認しましょう。
サポート体制も多言語に対応していると、外国の人が社内情報共有ツールの運用主体者になった場合でも安心です。
安全性
社内情報共有ツールのセキュリティ対策が十分に講じられていると、機密情報を安心して扱えます。暗号化通信・アクセス制限・監査ログ機能など、セキュリティに関する機能が豊富に搭載されているかを確認しましょう。
また、社内情報共有ツールの提供事業者が、セキュリティに関する認証を取得しているかどうかも重要な確認ポイントです。セキュリティに関する認証を取得している事業者は、第三者からセキュリティ対策を十分に講じていると認められているため、より安心して利用できます。
社内のストック情報をすぐに見つけられる管理ツール「NotePM」
社内Wikiの情報共有ツール4選
ここからは、社内Wikiの情報共有ツールとして、以下の4つを紹介します。
- NotePM
- esa
- Qiita:TEAM
- ナレカン
社内Wikiの情報共有ツールを導入することで、ナレッジを共有しやすいです。ナレッジ共有による業務効率化を行いたい人は、ぜひ検討してみましょう。
NotePM

NotePMはナレッジマネジメントの問題を解決する社内Wikiで、社内の情報共有として優れています。ウィキペディアのように従業員が簡単に書き込むことで、重要な情報を蓄積しているからです。従業員が欲しい情報をすぐに取り出せますし、更新管理が大変なマニュアルもWiki上で作成できます。口頭でやり取りしていた属人化になりやすいナレッジも簡単に管理可能です。
NotePMの特徴
- マニュアル作成・ナレッジ共有も簡単
- 全国で7000社以上が登録済
- 30日間すべての機能を無料お試し可能
NotePMがおすすめな人
- ナレッジを簡単に書き込める情報共有ツールを探している人
- 検索性に優れた情報共有ツールを使いたい人
料金プラン(月額)

NotePM
URL: https://notepm.jp/
>関連記事:マニュアル作成ツール比較20選【2025年最新】
>関連記事:【無料】業務マニュアルを簡単に作れるテンプレート10選!
社内のストック情報をすぐに見つけられる管理ツール「NotePM」
esa

esaは「情報を育てる」という視点で開発された、情報共有サービスです。業務の中で生まれる情報は個人ではなくチームで共有すべきという考えを元に、不完全な情報でも共有します。そこからチーム全員で何度も更新することで、常に最新状態に育てて、整理する仕組みです。豊富な入力補助機能の搭載、書き途中状態での共有機能、外部サービスとの連携も可能です。
esaの特徴
- 全員で情報を育てる同時編集エディタも搭載
- バージョン管理・ロールバックも容易
- 60日間無料お試し可能
esaがおすすめな人
- 同時編集機能で素早くナレッジを更新したい人
- バージョン管理をしやすい情報共有ツールを探している人
料金プラン(月額)
- 500円/1ユーザー
esa
URL: https://esa.io/
Qiita:TEAM

出典:Qiita Team – 日報やナレッジ共有に便利な情報共有サービス
Qiita:TEAMはメモ帳のような感覚で簡単に入力、共有できる社内向け情報共有ツールです。何でも書きたいと思える使い勝手の良さを秘めており、シンプルな操作で情報共有できます。
ナレッジはもちろん、会議の議事録、決定事項もシンプルな操作で共有可能です。社内に潜む暗黙知をなくし、チームの生産性を高められます。
Qiita:TEAMの特徴
- こまめな情報共有で生産性を高められる
- Markdown記法に対応したプレーンテキストで記載
- 7日間の無料トライアル可能
Qiita:TEAMがおすすめな人
- Markdown記法を使える情報共有ツールを利用したい人
- ナレッジだけでなく議事録も管理したい人
料金プラン(月額)
- 500円/1ユーザー(Personal)
- 1,520円/~3ユーザー(Micro)
- 4,900円/~7ユーザー(Small)
- 7,050円/~10ユーザー(Medium)
- 要お問い合わせ(Extra)
Qiita:TEAM
URL: https://teams.qiita.com/
ナレカン

出典:トップページ | 社内のナレッジに、即アクセスできるツール「ナレカン」
ナレカンは「社内のナレッジに、即アクセスできる」をコンセプトとした情報共有ツールです。
テキストベースでナレッジを保存でき、保管しているナレッジはキーワード検索で探せます。検索スピードは平均0.2秒と非常に速く、コンセプト通り社内のナレッジをすぐに見つけられます。
ナレカンの特徴
- テキストベースのナレッジを気軽に保存可能
- 検索スピード平均0.2秒のキーワード検索を利用できる
- AIのチャット機能を用いた検索も可能
ナレカンがおすすめな人
- ナレッジを素早く見つけられる情報共有ツールを探している人
- AIを使って簡単にナレッジを探したい人
料金プラン(月額)
- 要お問い合わせ
ナレカン
URL:https://www.narekan.info/
ビジネスチャット・SNSの情報共有ツール3選
ここからは、ビジネスチャット・SNSの情報共有ツールとして、以下の3つを紹介します。
- Slack
- Chatwork
- LINE WORKS
ビジネスチャット・SNSの情報共有ツールを利用すると、社内コミュニケーションが活発になります。情報共有だけでなく、社内コミュニケーションも促進したい人は、ぜひチェックしてみましょう。
Slack

Slackはチャット形式のビジネス向け情報共有ツールです。業務の連絡事項の投稿や、必要なファイルをチャット上にアップロードすることで、簡単にメンバーに共有可能です。グループ内でのチャットはもちろん、個人と直接やりとりすることもできます。
Slackを使えばチームメンバーが1ヶ所に集まり、一体となって活動が可能です。社外の人とも簡単に連絡を取れます。
Slackの特徴
- ビジネス用のメッセージアプリケーション
- チャンネルというスペースでメンバーとやり取り可能
- 無料で利用可能(一部機能制限有)
Slackがおすすめな人
- 無料で多くの機能を利用できる情報共有ツールを使いたい人
- AIでチャットの内容を要約できる情報共有ツールを使いたい人
料金プラン(月額)
- 無料(フリー)
- 1,050円/1ユーザー(プロ)
- 1,800円/1ユーザー(ビジネスプラス)
- 要お問い合わせ(Enterprise Grid)
Slack
URL:https://slack.com/intl/ja-jp
Chatwork

出典:チャットワーク – Chatwork | ビジネスコミュニケーションを早く、簡単に | Chatwork(チャットワーク)
Chatworkは中小企業向けのビジネスチャットです。導入すれば、意思決定のスピードアップ・業務効率アップ・社内コミュニケーションの活性化につながります。
チャットにはメッセージ検索・絵文字・ダイレクトチャット・マイチャット・ピン留めなど、豊富な機能がそろっています。そのほか、ビデオ・音声通話タスク管理、ファイル管理も可能です。
Chatworkの特徴
- 誰でも簡単に使えるシンプルな機能を搭載
- 国内利用者数No.1(2024年4月時点)のビジネスチャットツール
- 無料で利用可能
Chatworkがおすすめな人
- 無料で多くの機能を利用できる情報共有ツールを使いたい人
- シンプルなUIの情報共有ツールを使いたい人
料金プラン(月額)
- 無料(フリー)
- 924円/1ユーザー(ビジネス)
- 1,584円/1ユーザー(エンタープライズ)
Chatwork
URL:https://go.chatwork.com/ja/
LINE WORKS

出典:LINEとつながる唯一のビジネスチャット – LINE WORKS
LINE WORKSはビジネス版のLINEです。ビジネスチャットの中でも、唯一LINEと繋がれます。プライベートで使い慣れている方も多い、おなじみのチャット画面やスタンプ機能を使って業務のやり取りをできるため、コミュニケーションの活性化も期待できます。
トークやメール以外に、アドレス帳・掲示板・カレンダー・資料格納Drive・アンケートなど、豊富な機能がそろっている点も魅力です。
LINE WORKSの特徴
- 有料ビジネスチャットとして2023年度シェアNo1を達成
- 業務効率化に必要な機能をアプリに集結
- 30ユーザーまで無料で利用可能
LINE WORKSがおすすめな人
- フランクな雰囲気の社内コミュニケーションを促進させたい人
- カレンダー機能をはじめ、豊富な機能がそろっている情報共有ツールを使いたい人
料金プラン(月額)
- 無料(フリー)
- 594円/1ユーザー(スタンダード)
- 1,056円/1ユーザー(アドバンスト)
LINE WORKS
URL:https://line.worksmobile.com/jp/
社内のストック情報をすぐに見つけられる管理ツール「NotePM」
グループウェアの情報共有ツール4選
ここからは、グループウェアの情報共有ツールとして、下記の4つを紹介します。
- Microsoft 365
- Google Workspace
- サイボウズ Office
- desknet’s NEO
グループウェアの情報共有ツールを導入すると、情報共有以外にも幅広い業務を効率化できます。社内の生産性を全体的に見直したい人はぜひチェックしてみましょう。
Microsoft 365

出典:Microsoft 365 – 生産性向上アプリのサブスクリプション | Microsoft 365
Microsoft 365は、Microsoft社が提供する月額課金のグループウェアです。従来買い切り型のOffice製品WordやExcel、PowerPointを含め、Teamsなどのクラウド型のサービスも利用できます。
常に最新のバージョンを利用できるため、サポート終了やバージョン互換などを気にする必要もありません。導入済みのライセンス数も把握しやすく、利用状況も容易に把握できるツールです。
Microsoft 365の特徴
- 選択プランで利用可能なアプリケーションが異なる
- ソフトウェアはすべて自動更新対象
- 1ヶ月間の無料トライアル期間有
Microsoft 365がおすすめな人
- ドキュメント作成や表計算などを一つのツールで行いたい人
- バージョン更新に手間をかけたくない人
料金プラン(月額)
- 1,187円/1ユーザー(Business Basic)
- 2,474円/1ユーザー(Business Standard)
- 4,354円/1ユーザー(Business Premium)
- 1,632円/1ユーザー(Business Apps for business)
Microsoft 365
URL:https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365
Google Workspace

出典:ビジネスアプリとコラボレーションツール | Google Workspace
Google WorkspaceはGoogle社が提供するグループウェアです。元々G Suiteの名称で無償提供されていました。
Gmail・Web会議・チャット・カレンダー・ドライブ・スプレッドシートなど、個人や組織が成果を上げるための機能を利用可能です。また、共有ドライブを作成することで、従業員へのファイルの共有・同時編集も容易に行えます。
Google Workspaceの特徴
- 機能間のシームレスな連携も可能
- 安全な最新鋭のセキュリティ環境で利用可能
- 14日間の無料トライアル可能
Google Workspaceがおすすめな人
- Web会議ができる情報共有ツールを使いたい人
- セキュリティ機能に優れた情報共有ツールを使いたい人
料金プラン(月額)
- 800円/1ユーザー(Business Starter)
- 1,600円/1ユーザー(Business Standard)
- 2,500円/1ユーザー(Business Plus)
- 要お問い合わせ(Enterprise)
Google Workspace
URL:https://workspace.google.com/intl/ja/
サイボウズ Office
サイボウズ Officeは、中小企業向けのグループウェアです。社内の情報共有を支援するための、スケジュール共有・ワークフロー・掲示板・ファイル共有・ToDoリストなど、多くの機能を利用できます。
誰でも簡単に使えるように開発されており、導入しやすいツールです。パソコン、タブレット、スマートフォンなどさまざまな端末に対応しているため、いつでもどこでも気軽に操作できます。
サイボウズ Officeの特徴
- 累計導入社数70,000社を突破
- 20年以上ユーザーのニーズに合わせて進化
- 30日間すべての機能を無料お試し可能
サイボウズ Officeがおすすめな人
- 長年にわたって利用されている情報共有ツールを使いたい人
- 十分な無料トライアル期間で、ツールの使用感を試したい人
料金プラン(月額)
- 660円/1ユーザー(スタンダードコース)
- 1,100円/1ユーザー(プレミアムコース)
サイボウズ Office
URL:https://office.cybozu.co.jp
desknet’s NEO
desknet’s NEOは、業務課題をワンストップで解決できる、オールインワン業務改善プラットフォームです。ノーコード開発にも対応しており、業種や利用規模を問わない幅広い利用が可能です。
スケジュール・電子会議室・設備予約・回覧レポート・ポータル・アンケート・ワークフローなど、業務効率化に役立つ機能が豊富に搭載されています。
desknet’s NEOの特徴
- どのような組織にもフィットするグループウェア
- 業務アプリ作成など拡張機能を用意
- 30日間の無料トライアル可能
desknet’s NEOがおすすめな人
- ツール内で社内掲示板を利用したい人
- カスタマイズ性の高い情報共有ツールを使いたい人
料金プラン(月額)
- 660円/1ユーザー(ライト)
- 880円/1ユーザー(スタンダード)
- 1,100円/1ユーザー(プレミアム)
- 836円/1ユーザー(チャットプラス)
desknet’s NEO
URL:https://www.desknets.com/
オンラインストレージの情報共有ツール4選
最後に、オンラインストレージの情報共有ツールとして、下記の4つを紹介します。
- Dropbox Business
- セキュアSAMBA
- Fleekdrive
- Stock
オンラインストレージはインターネット環境さえあれば利用できるため、リモートワークを行っている人にとっても使いやすいです。社内情報共有ツールの一つの選択肢として、ぜひ検討してみましょう。
Dropbox Business

出典:Dropbox Professional とチーム向け Dropbox – 詳細 – Dropbox
Dropbox Businessは、法人向けのオンラインストレージです。接続端末を問わないことから、いつでもどこでも必要なデータにアクセスできます。
パスワードとファイル有効期限を設定できるため、ビジネス用のファイルをしっかりと保護できます。
個人用のプランもありますが、ビジネス用のプランでは1人3TBの容量を確保可能です。使いやすさ・信頼性・プライバシー・セキュリティを備えているため、企業の重要なファイルの保存に適しています。
Dropbox Businessの特徴
- 7億人以上のユーザーから信頼されているサービス
- ファイルの安全な保護と業界をリードする使いやすさを実現
- 30日間の無料お試しが可能
Dropbox Businessがおすすめな人
- 大容量のファイルを保管したい人
- パソコン操作に慣れていなくても使いやすいツールを探している人
料金プラン(月額)
- 無料(Basic)
- 1,500円/1名(Plus)
- 2,400円(Essentials)
- 1,800円/1名(Business)
- 2,880円/1名(Business Plus)
- 要お問い合わせ(Enterprise)
Dropbox Business
URL:https://www.dropbox.com/ja/business
セキュアSAMBA

出典:セキュアSAMBA – 法人向けオンラインストレージサービス
セキュアSAMBAは、法人向けのオンラインストレージサービスです。操作が簡単で、ファイル共有・編集・整理・管理などを容易に行えます。
フォルダ単位でアクセス権を設定でき、社内はもちろん社外ともファイルの共有・編集ができ、一元管理が可能です。自社サーバーから移行する場合、既存のフォルダ構成を維持できるメリットもあります。
セキュアSAMBAの特徴
- 8,000社以上が導入しており、継続率98%を達成
- デスクトップアプリの利用で、ファイルの直接編集や保存も簡単
- 無料で利用可能なフリープラン有(容量1GB 2名まで)
セキュアSAMBAがおすすめな人
- フォルダ単位で情報を管理したい人
- フリープランのある情報共有ツールを使いたい人
料金プラン(月額)
- 無料/~2名(フリー)
- 27,500円(スタンダード)
- 38,500円(ビジネス)
- 52,800円~(エンタープライズ)
セキュアSAMBA
URL:https://info.securesamba.com/
Fleekdrive

出典:企業向けオンラインストレージサービス Fleekdrive
Fleekdriveは、セキュリティ性能の高い情報共有ツールです。社内・社外の人と、パスワードで保護したURLを共有することで、簡単にファイルを共有できます。
ファイルをアップロードした際の連絡・上長からの承認など、ルーティン業務の自動化も可能です。
Fleekdriveの特徴
- URLを共有することでファイルを共有できるオンラインストレージ
- 社外の人とも安全にファイルを共有できる
- ルーティン業務を自動化できる
Fleekdriveがおすすめな人
- セキュリティ性能が高い情報共有ツールを使いたい人
- ルーティン業務の効率化を図りたい人
料金プラン(月額)
- 660円/1名あたり(Team)
- 1,980円/1名あたり(Business)
Fleekdrive
URL:https://www.fleekdrive.com/
Stock

出典:Stock(ストック)|チームの情報を、最も簡単に管理できるツール
Stockは、さまざまな業種で導入しやすい情報共有ツールです。ドキュメントにテキストベースで情報を記載して、Stock内で保管できます。
ドキュメント内に画像の挿入もできるため、複雑な内容の情報も簡単に管理できます。アプリを使用することで、オフライン環境でも情報の編集が可能です。
Stockの特徴
- 画像付きの情報を管理できる
- オフライン環境でも一部の機能を利用可能
- タスク管理の機能も搭載
Stockがおすすめな人
- 場所を問わずに使いやすい情報共有ツールを探している人
- 情報共有だけでなく、タスク管理も行いたい人
料金プラン(月額/ビジネスプラン)
- 無料(フリー)
- 2,750円/~5ユーザー(ビジネス5)
- 5,500円/~10ユーザー(ビジネス10)
- 11,000円/~20ユーザー(ビジネス20)
- 16,500円/~30ユーザー(ビジネス30)
Stock
URL:https://www.stock-app.info/
社内のストック情報をすぐに見つけられる管理ツール「NotePM」
情報共有ツール『NotePM』の導入事例
情報共有ツールを導入した事例について知っておくと、情報共有ツールを導入するメリットがより明確になります。
ここからは、情報共有ツールの一つである「NotePM」を導入した事例として、下記の3つを紹介します。
- スタートアップ税理士法人
- 株式会社Rocal
- 株式会社クラダシ
情報共有ツールの導入を迷っている人は、導入事例も参考にしてみましょう。
スタートアップ税理士法人

スタートアップ税理士法人は、スタートアップの企業を中心に、税務・労務・司法書士業務支援などを行っている会社です。会社が急成長すると同時に、業務に必要な情報や、企業理念などが全社員で共有しづらくなっていた点が課題でした。
NotePMを導入し、部署ごとに情報を整理したところ「ここさえ見れば大体のことがわかる」場所ができ、社内で円滑に情報共有できるようになりました。また、新入社員もNotePMのマニュアルを読むだけで業務の進め方がわかるため、新人教育のコストが大幅に削減されました。
>関連記事:【導入事例】組織拡大・多店舗展開による情報共有問題を解決。100人組織への成長を支えるナレッジ共有ツール – スタートアップ税理士法人
株式会社Rocal

株式会社Rocalは、全国の地方企業を対象にWebマーケティング業務を行っている会社です。社員のほとんどがリモートワークで仕事をしており、日報の提出が毎日できているかを管理しにくい点が課題でした。
NotePMを導入し、NotePM内で日報を提出してもらう形にしたところ、提出時にSlackやメールで通知されるため提出状況の管理が容易になりました。加えて、NotePMの導入によって議事録の作成と管理も容易になり、情報の一元化も促進されました。
>関連記事:【導入事例】Slackとの連携で日報の提出状況を簡単に把握!リモートワークならではの業務効率化に成功 – 株式会社Rocal
株式会社クラダシ
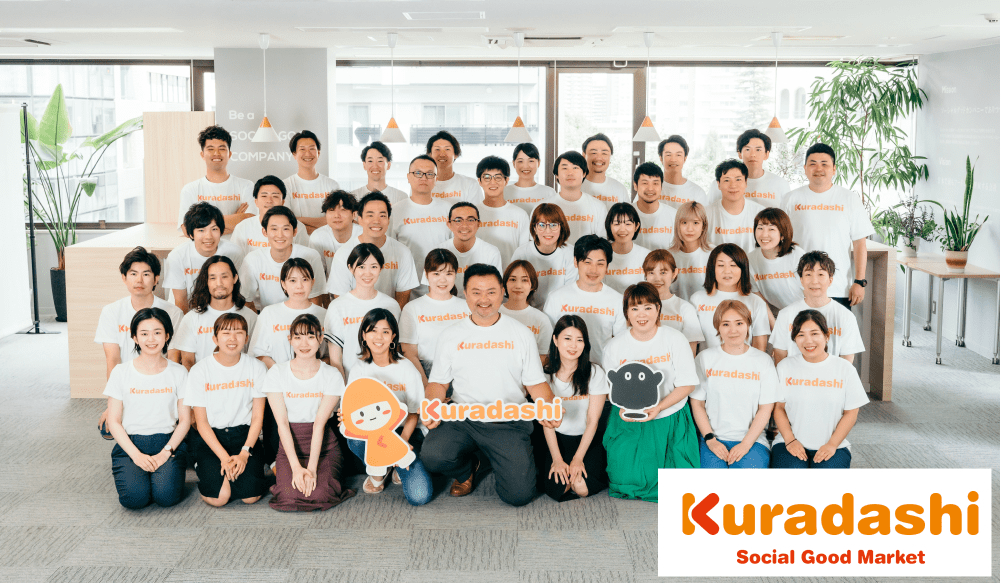
株式会社クラダシはECサイトの運営を行っている会社です。以前はGoogleドライブでナレッジ管理を行っていましたが、検索性が低く、欲しい情報にすぐアクセスできない点が課題でした。
NotePMを導入し、専門用語などをまとめた社内Wikiのページを作成したところ、社内Wikiを見るだけで業務に関する知識を身に付けられる環境が整いました。社内で用語の意味を質問するやり取りが減り、全体的に時間に余裕を持って業務を進められるようになりました。
>関連記事:【導入事例】成長企業のナレッジを手軽に一元管理! – 株式会社クラダシ
社内情報共有ツールを活用して業務を円滑に進めよう
本記事では、おすすめの社内情報共有ツール15選をはじめ、社内情報共有ツールの概要・種類・メリット・選び方も詳しく解説しました。
社内情報共有ツールには、Wiki・ビジネスチャット・SNS・グループウェア・オンラインストレージなどの種類があり、自社の目的や課題に応じた選択が必要です。
NotePMは、社内Wikiとして、社内のナレッジの共有・マニュアル作成にも対応しています。必要な情報をすぐ確認できるため、業務の属人化防止にも役立ちます。30日間無料でお試し可能なため、気軽に利用してみてください。

