「属人化」とは、特定の人のみが仕事のノウハウを抱えている状態のことです。
属人化は、企業が時代の変化に適応するためにはネックになっているといわれていて、属人化を解消するための「業務標準化」が求められています。一方で、属人化にはメリットが存在するのも事実です。
この記事では、属人化の意味や原因、メリット・デメリットを解説します。業務標準化の流れも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
関連記事:【2025年最新】ナレッジ共有ツールおすすめ16選(無料あり)導入事例も紹介
目次
属人化とは?
属人化とは、誰でもできる仕事を特定の人へ任せきりにしている状態をいいます。日本人のビジネスのスタイルは分業が基本であり、それぞれ自分が担当する業務を抱えているのが一般的です。そのため、特定の業務を担当する従業員が1人しかおらず、担当者以外はやり方を把握していないケースも珍しくありません。
言い換えると、業務が組織ではなく特定の個人に属した状態になっています。業務が個人に紐づいてしまう状態を属人化と呼び、批判的な意味合いで使用されることがほとんどです。かつては、IT分野のプロジェクト管理などでよく用いられていましたが、次第に他の分野や業種でも使われるようになりました。
属人化とスペシャリストの違い
属人化と似た意味の言葉に、スペシャリストがあります。スペシャリストとは個人のキャリア構築方法の一種であるのに対して、属人化は組織としての課題を指す言葉です。
スペシャリストは、特定領域に特化して、深く狭い知識やスキルを身に着けた人材のことをいいます。会計士や医師、エンジニア、料理人など、経験に基づく高度な専門知識が必要な職種では、スペシャリストの存在が目立ちます。
一方で、属人化は他の人にも任せられる状態にもかかわらず、業務がブラックボックス化されている状態を指す言葉です。まったく異なる概念の言葉であり、スペシャリストであっても、専門的なノウハウや知識を他の人に伝わるよう言語化することは可能です。
属人化と暗黙知の違い
属人化は組織運営上の問題状態、暗黙知は知識や技能の形態であることが根本的な違いです。
暗黙知とは、個人の経験や勘に基づく言語化が難しい知識やノウハウそのものを指します。
一方、属人化は、業務が暗黙知を持つ特定の個人に依存し、組織内で知識が共有されていない状態を意味します。
価値ある資産である暗黙知をマニュアル作成などで形式知へ転換し、組織全体で活用することが必要です。暗黙知の形式知化は、業務停滞といった属人化のリスクを回避し、組織全体の生産性向上につながります。
属人化を解消する「業務標準化」が注目を集める理由
近年では、社内の属人化を解消する業務標準化が重要視されています。背景には、次の2つの理由があります。
- 働き方の多様化
- 労働人口の減少
以下では、各理由を詳しく解説します。
働き方の多様化
かつての日本では終身雇用は当たり前でしたが、現在では転職や副業のハードルが大幅に下がりました。理由は、景気の悪化によって年功序列よりも成果主義を採用する企業が増えたことや、ジェンダーギャップの改善により働く女性が増えたことなどの社会変化が挙げられます。
総務省の「労働力調査」によると、2023年の転職者数は328万人に及んでいて、転職希望者の数は計測開始以来7年連続で上昇中です。
雇用が流動化したことで、業務ノウハウが企業に蓄積されづらくなりました。企業にノウハウを蓄積するため、中途社員を育成するためにも、属人化の解消が重要視されています。
労働人口の減少
少子高齢化にともない、社会全体で深刻な人手不足が発生しています。定年を迎えたあとにセカンドキャリアを築く人の人数は増加傾向にあるものの、64歳以下の労働力人口は横ばいの状態です。
パーソル総合研究所の推計によると、2030年には644万人の人手不足が発生するといわれています。後任を確保する難易度が上がるため、とくに人手不足が深刻な領域ではノウハウが引き継がれないまま、業務が属人化した社員が定年を迎えてしまうリスクがあるでしょう。
たとえば、IT業界では、レガシーシステムが問題視されています。レガシーシステムとは、企業の基幹システムや専用プログラムのうち保守・運用ノウハウが引き継がれなかったものを指します。
属人化を引き起こす4つの原因
そもそも、なぜ業務の属人化が発生するのでしょうか。主な要因は、以下の4点です。
- 業務の専門性が高い
- 実務で忙しくて時間がない
- ナレッジマネジメントが不十分である
- 教育や研修が不足している
属人化を防ぐためにも、まずは各原因を理解していきましょう。
業務の専門性が高い
専門性が高い業務は、特定の知識やスキルを持っていない従業員には難しい場合があります。専門性の高い業務を担当する人が、高度な知識や経験がない人にも伝わるように説明するのは困難です。
業務の標準化は容易ではないため、かなりの労力が必要になりますし、たとえ行えたとしても品質が低下するリスクもあります。そのため、他の人からは業務内容が理解できないままになり、属人化が進んでしまうでしょう。
実務で忙しくて時間がない
「属人化を解消したい」という意思はあっても、人手不足や業務負担の偏りなどが原因で、ノウハウの共有が後回しになってしまうこともあります。
業務負担を分散できないままになり、属人化がより進むという悪循環に陥ります。ワーク・ライフ・バランスを実現できないことが原因で、離職してしまうリスクがあるため要注意です。
ナレッジマネジメントが不十分である
業務に必要な知識やノウハウの総称をナレッジといい、ナレッジを共有・活用するための仕組みをナレッジマネジメントと呼びます。
ナレッジマネジメントでは、ただナレッジを共有する場を設けるだけでは不十分です。ナレッジを共有した人を評価する仕組みを作り、社員に「ナレッジを個人で独占するよりも共有したほうがためになる」と思わせる環境づくりが求められます。
教育や研修が不足している
教育や研修の不足は、属人化を引き起こす原因の一つです。
研修制度が整備されていない環境では、業務の進め方や専門知識が組織全体に共有されません。結果として、特定の担当者だけが業務内容を深く理解し、他のメンバーは対応できない状態に陥ります。
業務遂行に不可欠なコツや手順は、先輩社員など限られた人の暗黙知として蓄積されてしまいます。業務知識の偏在は、担当者不在時の業務停滞を招き、属人化を深刻な問題へと発展させるため注意が必要です。
属人化の4つのデメリット
属人化が批判的に捉えられることが多いのは、さまざまな問題の原因になりやすいためです。業務の大部分が特定の担当者に依存しているので、担当者が不在の場合や他の従業員が行う場合に、困った状況になることがよくあります。
属人化の主なデメリットは、以下のとおりです。
- 品質管理ができない
- ナレッジが組織に蓄積されない
- 業務効率が低下する
- ミスに気付きにくくマネジメントが難しい
以下では、属人化によって引き起こされる問題を具体的に紹介します。
品質管理ができない
属人化している業務を担当者以外が行った場合、同レベルの品質を維持するのは簡単ではありません。業務の遂行に必要な情報が共有されておらず、それまでの適切な方法で取り組めないためです。
試行錯誤して仕上げても品質が悪く、やり直しや修正を繰り返しても本来のレベルに達しないケースがよくあります。また、品質管理の基準が共有されていなければ、他の従業員はそもそも品質の良し悪しをチェックすることすら困難です。
上記のようなリスクがあるため、業務をやり遂げたとしても油断はできません。不具合が見つかるなど、品質に関する問題やクレームを想定した備えが必要になります。
ナレッジが組織に蓄積されない
担当者の退職にともない、ナレッジそのものが社内から失われてしまうリスクがあります。
業務ノウハウや知識が他の社員に共有されないため、後任の社員は1からナレッジを築くことになるでしょう。以前と同じ品質のサービスを提供できなくなるため、売上にも影響するかもしれません。
1971年〜1974年生まれの団塊ジュニア世代が定年退職する時期には、属人化したナレッジの喪失がとくに顕著になることが予想されます。
業務効率が低下する
業務効率の低下は、属人化によって起こりうる代表的な問題です。
担当者以外に行えない業務は、担当者が不在になっただけで停止しかねません。また、リスクを回避しようとして、代わりの従業員が担当しても状況が好転しない場合もあります。慣れていないので適切に進めるのが難しく、いたずらに労働時間が増えることになりやすいからです。
さらに、一つの業務の停滞がボトルネックとなって、後のフローに該当する業務がすべて遅くなってしまうケースも見受けられます。結果として納品が間に合わないなど、信用や利益を損ねる事態に発展することも少なくありません。
属人化は、広範囲にわたって業務効率が低下することもあるので注意が必要です。
ミスに気付きにくくマネジメントが難しい
業務でミスをしたときは、損害の拡大を防ぐために迅速な対処が必要です。したがって、周囲の指摘や担当者の申告によって、少しでも早くミスを明らかにしなければなりません。
しかし、属人化が進んでいる職場は、ミスはなかなか発見されなくなってしまいます。業務の進捗や状況を透明化できず、担当者が気付かなかったり隠したりすると、周囲が察知するのは困難だからです。
また、属人化が恒常的で従業員が各自の業務に専念していると、情報共有する必要性を感じにくくなります。ミーティングなどの機会が減れば、さらにミスの発覚が遅れがちになるので気を付けなければなりません。
属人化により得られる4つのメリット
業務は標準化しておくのが好ましいという風潮が見られるものの、実際には属人化にもメリットがあります。やみくもに標準化するのではなく、業務の性質や難易度を考慮したうえで判断するのが得策です。
属人化により得られる4つのメリットは、以下のとおりです。
- 仕事への責任感やモチベーションを高めやすい
- 顧客や他社員から信頼されやすくなる
- 短期的に業務効率が向上する
- 担当者の専門性や知識が高まる
以下では、各メリットをより詳しく解説します。
仕事への責任感やモチベーションを高めやすい
「この仕事は〇〇さんにしか任せられない」という状況に置かれることで、社員に責任感が芽生えやすくなります。頼られていることでやり甲斐を感じ、仕事のモチベーションもアップするでしょう。
ただし、人によっては責任が重荷になるケースもあるため、デメリットとして働くこともあります。
顧客や他社員から信頼されやすくなる
営業職や販売職のような職種では、社員の個性や人柄が売上に影響することも多くなっています。顧客と相性のいい社員が毎回窓口として担当することで、信頼関係を深められ、売上アップにつながるでしょう。
また、社内においても同様に、「わからないことがあっても〇〇さんに聞けば解決する」という状態にすることで、確固たるポジションを築くことが可能です。
短期的に業務効率が向上する
知識や経験が豊富な人が担当するため、業務を安定した品質で、スピーディーに進められるでしょう。さらに、人材教育に割く時間もかからないため、実務に専念できます。
ただし、担当者が異動や退職になるとノウハウが継承されないため、同じ品質のサービスを永続的に提供することが難しい点には注意が必要です。
担当者の専門性や知識が高まる
属人化は、担当者の専門性や知識を高めるメリットがあります。
特定の個人が業務を一貫して担当することで、業務に必要な知識・技能・経験が深く蓄積され、より高い品質や効率、創造力での業務遂行が可能です。とくにデザインや法務、会計など専門性が求められる業務では、継続的な担当が個人のスキルアップに直結するでしょう。
同じ業務にじっくり取り組む環境は、作業の細かいポイントやトラブルの予防策など、単なるマニュアルでは伝わらない暗黙知の体得を促す点もメリットとなります。
属人化を避けたほうがよい業務
属人化は個人の専門性を高める側面もありますが、組織運営上、積極的に解消すべき業務があります。とくに属人化を避けるべき業務は、以下のとおりです。
- バックオフィス業務
- 顧客対応・ヘルプデスク業務
- トラブル・セキュリティ対応業務
- 業務やプロジェクトの進行管理
安定した事業継続のため、標準化と情報共有が必要な業務を具体的に解説します。
バックオフィス業務
経理や人事などのバックオフィス業務は、属人化を避けるべき業務の代表例です。
決算数字や人事考査など、企業の根幹に関わる重要な情報を扱うため、業務の標準化が重要です。担当者個人に依存せず、誰が担当しても同じ手順で、同じ品質の業務を遂行できる体制が求められます。
担当者ごとに業務の進め方が異なると、他の従業員が手続きなどで混乱を招きます。万が一、担当者が急に休んだり退職したりした場合、業務が完全に停止してしまうリスクがあるため注意が必要です。
顧客対応・ヘルプデスク業務
顧客対応やヘルプデスク業務は、属人化を避けるべき業務です。
企業のブランドイメージや顧客満足度に直接影響するため、対応品質の標準化が必要です。担当者によって顧客への回答内容や対応が異なると、「言っていることが違う」といったクレームにつながり、顧客を混乱させたり不満を抱かせたりする可能性があります。
また、特定の営業担当者のみが顧客情報や商談履歴を把握していると、担当者不在の際に他の従業員が対応できず、機会損失やトラブルに発展する危険性があります。
トラブル・セキュリティ対応業務
システムトラブルやセキュリティ事故が発生した際の対応業務は、属人化を避けるべき業務に挙げられます。トラブルやセキュリティインシデントは、発生時に迅速かつ正しい手順で対応することが、被害を最小限に抑えるうえで重要です。
業務が属人化していると、担当者によって対応方法が異なり、初動が遅れたり、誤った対処をしてしまったりする可能性があります。セキュリティ対応では、不適切な手順が情報漏洩の範囲を広げるなど、かえって被害を拡大させてしまうおそれがあるため注意が必要です。
業務やプロジェクトの進行管理
営業部門の顧客管理や各種プロジェクトの進行管理は、属人化を避けるべき業務です。
プロジェクトの進め方や管理方法が担当者ごとに異なると、タスクの進捗や課題などの情報が一元化されません。組織として全体の状況を正確に把握できなくなり、適切な意思決定が困難になります。
担当者が不在の場合、他の従業員による業務の引き継ぎやサポートが不可能となり、業務停滞を招いてしまいます。担当者不在による業務の停滞は、プロジェクト全体の遅延につながるリスクがあるため注意しましょう。
属人化しても問題ない業務
属人化は組織にとってリスクと見なされがちですが、すべての業務で解消すべき問題というわけではありません。業務の性質によっては、むしろ特定の個人の能力に依存することが、高いパフォーマンスや組織全体の利益につながるケースもあります。
具体的には、以下のような業務が該当します。
- 高度な専門性や特殊スキルが必要な業務
- 迅速な意思決定や柔軟性が必要な業務
どのような業務が属人化と相性がいいのか、以下で詳しく解説します。
高度な専門性や特殊スキルが必要な業務
高度な専門性や特殊スキルが必要な業務は、属人化が許容される業務の一つです。
研究開発や高度なコンサルティングなど、特定の個人の専門知識や技術が企業の競争力の源泉となる分野では、属人化がむしろ強みとなります。代替が困難な個人の能力が、他社にはない独自の価値を生み出すため、組織として意図的に属人化を選択する場合もあります。
また、一人の担当者が業務を深く担うことで経験が集中し専門性がさらに高まり、結果として担当者自身のスキルアップが促進されるというメリットにつながるでしょう。
迅速な意思決定や柔軟性が必要な業務
迅速な意思決定や柔軟性が必要な業務では、属人化が効率化につながる場合があります。
状況変化への素早い適応が必要な短期プロジェクトなどでは、担当者に裁量権を集中させれば、承認プロセスを短縮し、スピーディーな業務遂行が可能になります。また、従業員一人ひとりの特性や得意分野に合わせて業務を任せることは、個人の能力を最大限に引き出すことにつながるでしょう。
担当者の裁量を尊重する進め方は、業務効率のみならず、モチベーションの向上も期待できます。
属人化を解消するメリット
属人化の解消は、担当者不在時のリスクを回避するだけでなく、組織全体に多くのプラスの効果をもたらします。属人化を解消することで得られる主なメリットは、以下のとおりです。
- 業務の品質を向上させることができる
- 生産性の向上と業務効率化につながる
- 従業員の負担軽減につながる
- 予定外の出来事にも柔軟に対応できる
各メリットが組織にどのような価値をもたらすのか、以下で具体的に解説します。
業務の品質を向上させることができる
業務品質の向上は、属人化を解消するメリットの一つです。
業務手順をマニュアル化し共有しておくと、担当者の能力や経験にかかわらず、誰が担当しても一定の成果を出せるようになります。担当者によって生じていた品質のばらつきがなくなり、組織全体の業務品質が安定するでしょう。
さらに、マニュアル作成の過程で、作業におけるミスが起きやすい点や重要なチェックポイントが明確になります。情報を組織全体で共有すれば、人為的なミスを未然に防ぐ効果も期待できます。
生産性の向上と業務効率化につながる
属人化解消は、生産性の向上と業務効率化につながります。
業務の属人化は、担当者以外にプロセスが見えない業務のブラックボックス化を引き起こします。業務手順を標準化して全体像を可視化すると、非効率な作業や無駄な工程を発見し、改善を進めることが可能です。
また、標準化されたマニュアルがあれば、新入社員や異動してきた社員でもすぐに一定の品質で業務を遂行できます。特定の個人に依存しない体制は、組織全体の効率的な運営を実現可能です。
従業員の負担軽減につながる
属人化を解消するメリットとして、従業員の負担軽減につながることが挙げられます。
特定の担当者に業務が集中する状態は、従業員個人の精神的・肉体的な負担を増大させるだけでなく、急な欠勤や退職時に業務が停止するリスクを招きます。属人化を解消して業務を共有化すれば、担当者が不在の場合でも他の従業員が対応できるため、安心して休暇を取得できるようになるでしょう。
また、業務全体の状況が把握しやすくなれば、特定の従業員への業務の偏りをなくし、負担を組織全体で均等化することも可能です。
予定外の出来事にも柔軟に対応できる
予定外の出来事へ柔軟に対応できる体制を築けることは、属人化を解消するメリットの一つです。
業務の進め方やノウハウが組織全体で共有されるため、特定の担当者が不在でも他のメンバーが即座に業務を引き継ぎやすくなります。標準化された手順書やマニュアルが整備されれば、複数の社員が多様な業務に対応可能となるでしょう。
結果として、担当者の急な病気や退職、休暇などの予定外の事態が発生しても、業務を停止させることなくスムーズに継続できる組織が実現します。
属人化を解消する「業務標準化」の方法
スムーズに標準化を成功させたいなら、正しい手順を把握したうえで取り組むことが重要です。属人化を解消する「業務標準化」の具体的な方法は、以下のとおりです。
- 属人化の実態を把握して業務フローを整理する
- 業務マニュアルを作成する
- マニュアルをもとに業務の分散化を進める
- PDCAを回す
以下では、具体的な流れを4つのステップに分けて説明していきます。
属人化の実態を把握して業務フローを整理する
標準化の最初のステップは業務フローを明確にすることです。
属人化が起こっている業務を特定して、どのように作業を進めているのか把握しなければなりません。表面的にチェックするだけではわからないことが多いので、担当者に直接確認して調べることが重要です。
ヒアリングしたい箇所をリストアップし、担当者と共通認識を持つことによって、抜けがなく精度の高い情報を得やすくなります。属人化している箇所を十分にヒアリングした後は、業務フローを把握しやすくするためにフローチャートなどの制作が必要です。
業務マニュアルを作成する
業務フローが明らかになったら、マニュアル化して他の従業員も理解できるようにする必要があります。ただし、いきなり情報が網羅されたものを作ろうとするのは効率的ではありません。
まずはフローチャートなどをベースにして、一連の流れがわかるような簡易なマニュアルを用意します。そして、内容を付け足したり読みやすく編集したりして、少しずつブラッシュアップしていくと作りやすいでしょう。
マニュアルを改善していく過程で、担当者へのヒアリングを実施し、得られた情報を反映していくことで完成度を高められます。
マニュアルをもとに業務の分散化を進める
マニュアルを作成した後は、他の従業員に読んでもらい、業務を分散できる状態を目指します。1人ずつ配布する方法もありますが、情報共有ツールを活用するなどの工夫をすると周知しやすいです。
また、属人化が進行する原因として、担当者への権限の集中が挙げられます。権限を持たない他の従業員は、該当業務の遂行を自分の役割だと認識するのが難しく、責任がないように感じることも珍しくありません。そのため、業務を分散するときは、責任も分担することを明確に伝えることが重要です。
PDCAを回す
標準化した業務フローを実践してみたものの、ムリやムダが見つかる可能性も十分あります。また、状況が変化したことで、以前の業務フローが合わなくなるケースもあるでしょう。
標準化によってかえって業務効率や品質が低下してしまわないよう、現場の声を聞きながら定期的に見直しや改善に取り組むことが大切です。事前にモニタリングのための指標を設けたうえで、PDCAサイクルを回していきましょう。
属人化解消を成功させるためのポイント
属人化の解消は、組織にとって重要な課題ですが、簡単に解消できるわけではありません。解消を成功させるには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- アウトソーシングを検討する
- コミュニケーションを積極的に取る
- 属人化の解消を効率的に行う方法
各ポイントを理解し、自社の状況に合わせて取り組むことで、スムーズな移行を実現できるでしょう。
アウトソーシングを検討する
アウトソーシングの検討は、属人化解消に効果的な手段の一つです。
成功のためには、どの業務を委託できるか具体的に見極め、自社に合った委託先と運用形態を選ぶことが重要です。ヘルプデスクや従業員用PCの初期設定、ネットワーク・サーバーの構築・保守、セキュリティ対策などの専門知識が求められる情報システム部門の業務はアウトソーシングに適しています。
ただし、アウトソーシングは単なる業務の丸投げではありません。委託後も品質や進捗を管理するなど、発注者としての責任感を持ちましょう。
コミュニケーションを積極的に取る
積極的なコミュニケーションは、属人化解消を成功させるうえで重要なポイントです。
情報共有を促進し、協力体制を築くためには、日常的な交流を生み出す具体的な施策が求められます。とくに、上司と部下が1対1で定期的に対話する機会を設けることは重要です。業務の進捗確認だけでなく、キャリアの相談なども含めて話せば、互いの間に深い信頼関係が構築されます。
築かれた信頼関係は、日頃の円滑な情報交換を促し、風通しのいい組織風土の醸成につながるでしょう。
属人化の解消を効率的に行う方法
属人化を効率的に解消するには、ITツールの活用が効果的です。業務の属人化を防ぎ、誰でも業務を遂行できる状態を整えるには、業務プロセスの可視化と標準化が必要になります。
そこで推奨されるのがナレッジマネジメントツールです。従業員が持つ知識やノウハウを組織全体で共有・活用する仕組みを効率的に構築できます。
なかでも、社内のナレッジやノウハウを一元管理できる「NotePM」の活用がおすすめです。
NotePMは、特定の個人に依存していた暗黙知を組織全体の資産として共有・蓄積する環境を提供します。そのため、業務の標準化が促進され、属人化の解消に貢献するでしょう。
「NotePM」によって属人化を解消した事例
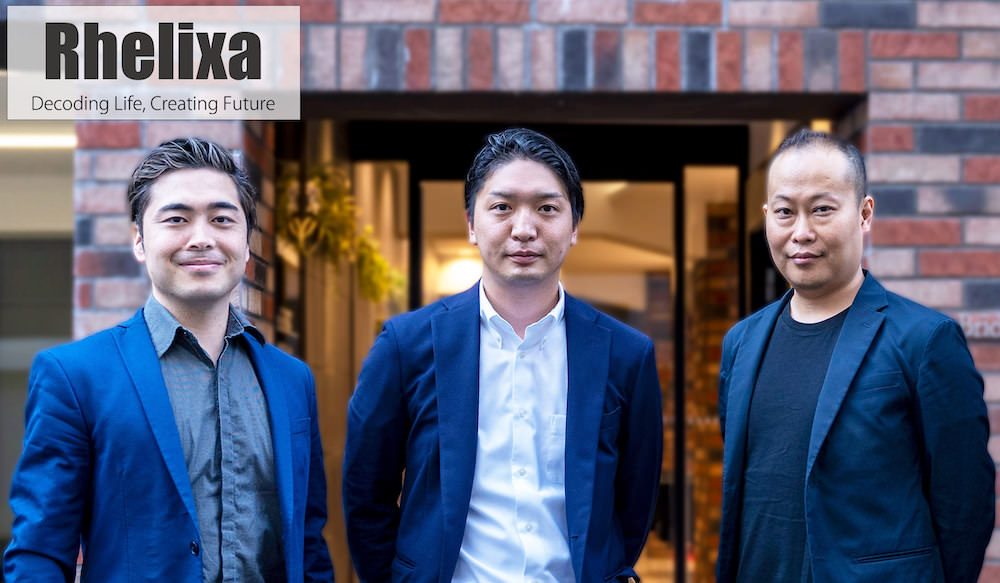
株式会社Rhelixaは、ノウハウの属人化という課題を解決するため、ナレッジマネジメントツールNotePMを導入しました。以前は提案内容や解析方法など専門知識が個人に偏り、業務品質にばらつきが生じていたことが課題の一つでした。
NotePMで知識を組織的に蓄積・共有する体制を整えたところ、ナレッジ共有に対する社員の意識が変化したようです。結果として、関連業務の知識が組織全体で身につき、社員のスキルアップと業務品質の安定につながっています。
関連記事:【導入事例】属人化していたノウハウや解析事例を社内共有。医師・学術分野の研究をサポート – 株式会社Rhelixa
属人化を防いで業務効率化を図ろう
ビジネスにおける属人化とは、誰でもできるはずの仕事が、特定の社員にしか任せられなくなっている状態を指す言葉です。
働き方の多様化や人口減少などの社会問題を抱えるなかで、属人化をそのままにしていると、経営に悪影響を与えるリスクがあります。ただし、属人化にもメリットはありますので、すべての業務において属人化を解消すればいいわけではありません。
自社にとって適切な範囲で、業務標準化を進めていきましょう。属人化解消を成功させるには、便利で使いやすいITツールを活用するのがおすすめです。




